本日の本紹介は、
僕も好きな著者、組織心理学者の『アダム・グラント』さんが書いた
【ORIGINALS誰もが『人と違うこと』ができる時代】
を紹介させていただきます。
ORIGINALS誰もが『人と違うこと』ができる時代
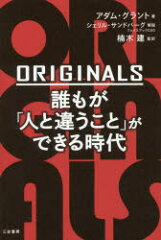

著者の紹介
アダム・グラント
ペンシルベニア大学ウォートン校の教授であり、組織心理学者で、
アメリカのビジネスや、ファイナンスに特化した雑誌『フォーチュン』誌の『世界でもっとも優秀な40歳以下の教授40人』や、『世界でもっとも重要なビジネス思想家50人』のうち1人に選ばれるなど数々の受賞歴をもち、
『Google』『ディズニー・ピクサー』『ゴールドマンサックス』などの一流企業や組織でコンサルティングおよび講演活動も精力的に行っている方である。
僕自身も、以前読んだアダムグラントさんの世界的ベストセラー【GIVE&TAKE】がとても好きで、
友達に一度譲ってしまったのですが、改めてもう一度買ってしまうほど興味深い1冊でした。
今回はそういった経緯もあり、同著者の他の本も読んでみたいと思い、手に取った経緯であります。
この本から学んだ事
変化の激しい時代と言われいる今、最近では当たり前のように耳にする個人の時代という言葉。
その言葉の中には一人一人が自分の強みを活かしていく事で好きな事ができるということではあるが、
ただ何食わぬ顔で生きていてもそれが叶うことは限りなくゼロに近い。
AIや機械の発達により便利なものや、情報が量産できる時代にどうやって個人を生かしていくかと考えたときにたどり着くのが、本書でいう
オリジナル(人と違うこと)
を見つけ磨き続けること。
この本にはそんな自分のオリジナリティを高め、他者よりも抜きん出た魅力を発揮するための方法が凝縮された一冊です。
この本を読んで僕が気になったところや、覚えておきたいと思った点を3つ紹介します。
- 変化を生み出す創造的破壊(ブジャデ)
- 賢者は時を待ち、愚者は先を急ぐ
- 厳しいしつけの落とし穴
変化を生み出す創造的破壊(ブジャデ)
まず、本書でいうオリジナルな人というのは、
『自らのビジョンを率先して実現させていく人』
とあります。
著者が10年以上にもわたり研究してきた中で、オリジナリティが高く、結果を出してきた人の最たる特徴として
既知のものを疑い、より良い選択肢を探すことに長けている。
という事でした。
その中で必要になってくるのは好奇心であり、『デジャブ』ならぬ、
『ブジャデ』の発想であると著者は述べています。
『デジャブ』とは初めて見たものなのに、前にも見たことがあるとういう感覚であり、
ここでいう『ブジャデ』とは、その反対で既知のものを前にしながら、新たな視点でそれを見つめ、古い問題から新たな洞察を得ること
とあり、数々の発明家や、企業の経営者たちは得てしてこの『ブジャデ』の体験から創り上げられることが多いと述べられています。
本書にはそんな『ブジャデ』の体験について、研究結果を用いて、学生4人が起業したアメリカのメガネ会社『ワービー.パーカー』の話を中心に、いくつもの例が紹介されています。
賢者は時を待ち、愚者は先を急ぐ
この本を読んだ中でも、僕自身が特に考え直させられた点の一つが
あえて『先延ばし』をする
ということ。
この本では【戦略的先延ばし】として
良いアイデアや、クリエイティブな仕事ほど、先延ばしが有効的と述べられています。
一般的には、スピード重視や、質より量、即行動、締切の前にはしっかり終わらせる事が、求められているとよく聞きますが、
著者がオリジナルな人を研究した中で、クリエイティブ能力の高い人や、問題解決能力に秀でている人の多くは、物事を先延ばしにする特徴があることがわかったとしていました。
その例の1つとしてこの本では、レオナルド・ダ・ヴィンチが挙げられています。
ダ・ヴィンチの名作で知られる『モナ・リザ』は1503年から描き始め、何年かの間は描いてはやめるということを繰り返したのちに放置し、亡くなる直前の1519年になってやっと完成させたとのこと。
ここでのダヴィンチの何もしなかった一見ムダな時間こそが、オリジナリティにとって欠かせなかったと歴史研究家のウィリアムパナパッカー氏も解説しており、
レオナルドは途中、球体を照らす光の研究をしていたが、そのおかげで『モナリザ』と『洗礼者聖ヨハネ』の一連の絵画で一体感を出すことができた。
絵画の作成は遅れたが、光学の実験があったからこそ最終的にあのような絵画が出来上がったのだ。
と本書でも述べられていました。
一見無駄のようなことでも、それがアイデアを生むための鍛錬になったり、習熟期間になったりするということでもあり、
ダ・ヴィンチ自身も急いではオリジナリティを発揮できないこともわかっていて
『天才は最小限しか仕事をしないときこそ、もっとも多くを成し遂げることがある。そういうときに天才は、発明を考えだし、頭の中で完璧なアイデアを形づくっているからだ』
と言っていたそうです。
問題解決力に秀でていて、オリジナリティの高い人程、
戦略的に先延ばしをして様々な可能性を試し、改良する事によって、唯一無二のものを創り上げていく傾向があるとのことでした。
厳しいしつけの落とし穴
また、本書では出生順位でのオリジナリティの研究もいくつか紹介されており、
第一子よりも、第二子、第三子と兄や姉が多いほど、他の兄弟から学ぶ時間が多くなり、リスクを冒すことや独創的なアイデアに寛容な傾向かがあると述べられていました。
そのの理由の一つとして、第一子は親に厳しく躾けられるのに対し、
下になるにつれてだんだんと親の躾も寛容になり、ルールが緩みがちになっていくため、見逃してもらえる機会が増える傾向にあり、
結果、あと生まれの子供のほうが、失敗を臆せずに行動でき、何ごとにも挑戦的である傾向があるとのことでした。
確かに僕の周りでも、長男は慎重型で面倒見の良い子が多く、
次男はヤンチャで好きなことをやっている人が多いように感じます笑。
本書でも、オリジナルな人の多くがリスクテイカーなのは、周囲が自主性を尊重してくれたり、守ってくれるからである、と述べられていました。
あんまり厳しくしつけし過ぎると、子供の自主性を損なわせてしまう傾向があるということなんですかね(^^)
こんな人におススメ
僕自身も、昔から協調性が欠けていたり、人と合わす事が苦手で悩んでいた事もありました。
『変わっている』と言われることもあり、昔はそれがコンプレックスで少しでも常識を学び、普通でいることに努力していました。
しかし、最近は読書や色んな人と会い、様々な価値観を感じていくにつれて、人それぞれでみんな違って良いんだ、と思うように考え方が変わってきました。
そして、この本を読んだときにそれが僕の中で確信に変わり、少し安心することができました。
僕はまだまだ頑張っていても良い、明るい未来の可能性もあるんだと改めて感じます。
本書は、そんな普通でいる事に悩んでいる人や、変わっていると思われている人に救いの手を差し伸べる一冊になるのではないかと思います。
僕が読んだ本を不定期で投稿している、学びの為の読書アカウントをこちらからフォローしていただけたらめちゃくちゃ喜びます(^o^)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30fb47ba.d4086a51.30fb47bb.421bbde6/?me_id=1207018&item_id=12350013&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru2%2Fcabinet%2Fb%2F7%2F683%2F9784837957683.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
ORIGINALS誰もが「人と違うこと」ができる時代
価格:1,980円(税込、送料別) (2023/3/28時点)


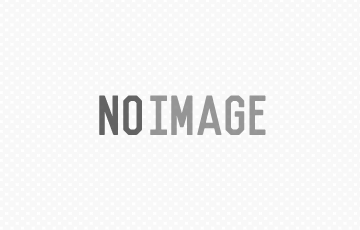
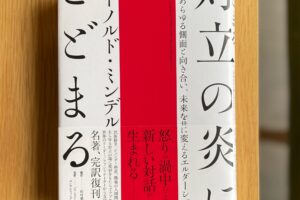
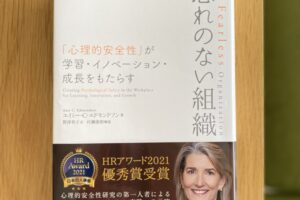
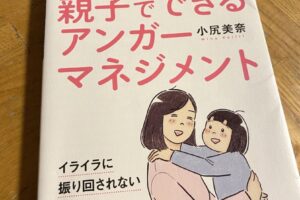

最近のコメント